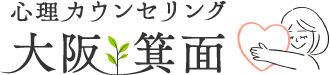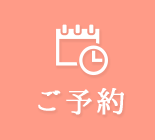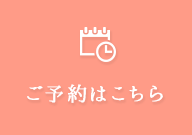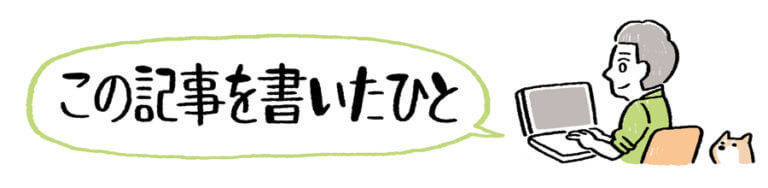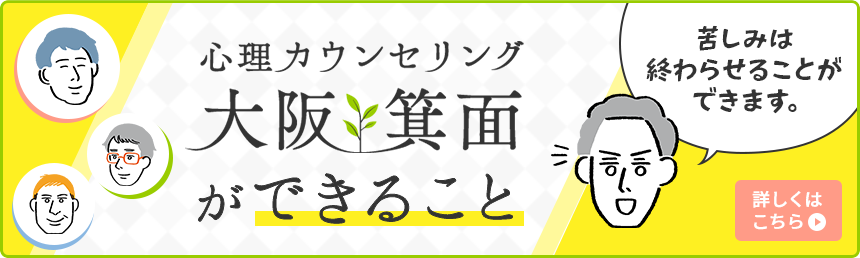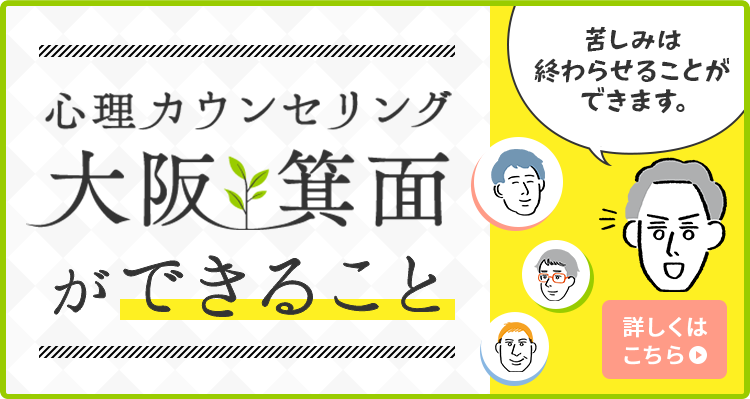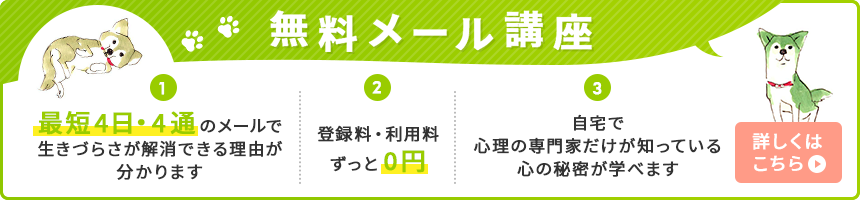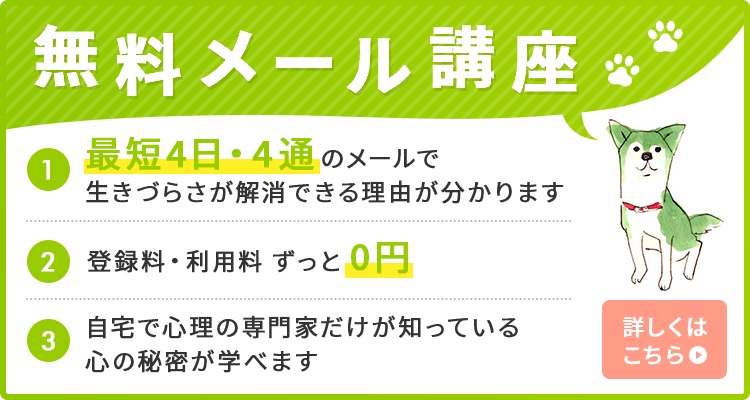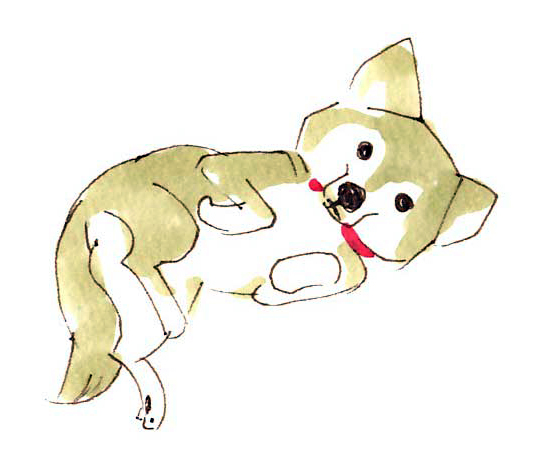
泣きたくなる子育て、笑顔になる子育て


子育てって
年中無休だから
ほんとに大変だと
感じてるよ
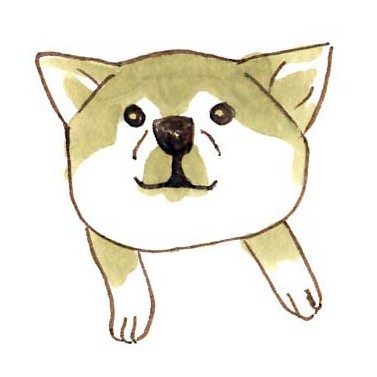
あたしも子育てが
大変過ぎて脱毛症
になっちゃった
よね(涙)
今回は、10年以上親子・子育て問題
の解決をサポートし続けてきた
心理カウンセラーが考える
「親も子供も笑顔になる子育て」
親にも子供にも笑顔を増やす
子育てのコツと方法
について解説させて頂きます。
お読み頂ければ、
1日の休みも無く、気力、体力を限界まで
すり減らす日が毎日続いていくことで、
思わず泣きたくなってしまう日もある
子育ての日々の中で、
親にも子供にも
笑顔を増やすことができるヒント
がきっと見つかると思います。
心理カウンセラー
長谷川貴士です
- 1:子育ては泣きたくなるくらい辛い?
自然な子育て、不自然な子育て - 2:「親も子供も笑顔になる子育て」
を実現するために
重要な3つのポイント - 3:子育てで最重要なのは
親の心からの笑顔? - 4:自分の子供が「分からない」と
感じる時にある不安と混乱 - 5:親子といえども
相性の良し悪しがある - 6:子供への期待値を下げてみる

1:子育ては泣きたくなるくらい辛い?
自然な子育て、不自然な子育て
子育てをしていて、
「毎日楽しい感じしかありません!」
こう答えることができる方は
少数派だと感じています。
実際に厚生労働省が実施した
「21世紀出生児縦断調査」の結果には、
子育てに負担を感じている親の割合は
87.7%となっていました。
上記の調査結果の中で述べられている
子育て中の親が子育てにおいて
負担に感じることのベスト3は
以下の3つでした。
<1位>(64%の親が該当)
自分の自由な時間が取れない
ことで子育てに負担を感じる
<2位>(39%の親が該当)
育児に疲れているので、
子育てに負担を感じている
<3位>(34%の親が該当)
子供から片時も目が離せず
気が休まらないことで
子育てに負担を感じている
私の子育ての実感では、
上記の<1位~3位>のどれもが
自分にも当てはまるなぁ、
よく分かるなぁ、と感じています。
それでは、なぜ?子育てが大変なのか。
ただ、大変なのではなく、子育てが
泣きたくなるぐらい大変なのはなぜか?
それは、今の子育てが、
「不自然な子育て」になって
しまっているからでした。
子育てが泣きたくなるくらい
つらいこととして感じられる
「不自然な子育て」とは
どんな子育てなのか?
「不自然な子育て」の反対側にある
「自然な子育て」とは
どんな子育てなのか?
を解説させて頂く前に、
「親も子供も笑顔になる子育て」
親にも子供にも笑顔を増やす
子育てのコツと方法
の軸となる3項目を先に
お伝えさせて頂きますね。
それは以下の3項目です。
<1>
「親の個性と子供の個性は、
まるで違う時があることを理解する」
<2>
「親は子供に笑顔を向け続けること
いつでもご機嫌でいること
そのために、自分の機嫌が良くなることを
できる限りすること」
(自分の機嫌が良くなることを
できる限りすることを自分に許すこと)
<3>
「子育に、保護とトレーニングの
視点を持つこと」
この3項目を押さえて頂ければ、
子育てが泣きたくなるくらい
つらいこととして感じられる
「不自然な子育て」のさなかにあって
日々奮闘していたとしても、
自分にも子供にも笑顔を増やす
ことができるきっかけやコツが
きっと見つかることと思います。
それでは、まずは、
子育ての辛さを作っている
根本の原因である、
「不自然な子育て」と
その反対側にある
「自然な子育て」とは
何かについて解説させて頂きますね。
< 不自然な子育て >とは?
「不自然な子育て」とは何か?
の実例として、
私(カウンセラー長谷川)の
「不自然な子育て」体験談から
ご紹介させて頂きます。
(私(カウンセラー長谷川)の
「不自然な子育て」体験談)
子育てって、本当に、
ほんとーに大変ですよね。
わが家も2人のやんちゃな男の子の
子育てに日々奮闘し続けています。
毎日しっちゃかめっちゃかです(泣)
( 総務省・子育て参加時間の調査結果 )総務省が行った
2021年度「社会生活基本調査」によると、
6才未満の子供が居る家庭では、
家事・育児に費やす時間は、平均すると1日当たり男性が約2時間、
女性が7時間30分のようです。
全国平均が上記の通りの中で、
私が家事・育児をしている時間は、
平均すると1日当たり7時間20分です。
ですので、人並みに子育ての大変さを
実感できていると思います。
私は個人開業のカウンセラーで、
フルタイムで働いています。
子供が生まれてからは休日を増やして
年間120日ほど休日にしています。
その休日は1日14時間ほど
育児、家事をしています。
私の妻は毎日、私が家事・育児をしている
時間の平均である7時間20分の2倍以上の
18時間は家事・育児をしています。
自宅保育のご家庭であれば、
どのご家庭でも似たようなご状況かと思います。
私はこの何年も妻が家事と育児をしている
姿しかほぼほぼ見たことがありません。
私は妻の家族に対するこの献身に
ほんとうに頭が上がりません。
とはいえ、妻が研修やお見舞いなどの時には
私も一人で二人の男の子の世話を8時間ぐらい
することがあります。
そんな時に子供の体調や機嫌が悪いと
本当に泣きたくなるくらい大変でした。
大人(私)1人で、子供2人の遊んでくれ、
世話してくれ、手伝って欲しい、
あれが欲しい、ここが痛い、
あれを壊した、失敗した、あっ危ない!
などなどの無限に続く要求(リクエスト)と、
危険回避に応え続けながら、
無限に散らかり続ける、
おもちゃ、食器、食べこぼし、飲みこぼしを
片づけながら、家事を進めていくのは、
本当にほんとーーーに、骨が折れますよね。
ご飯を作って、出して、食べさせて、片づけて、
おやつを出して、食べさせて、片づけて、
また、ご飯を作って、食べさせて、片づけて、、、
この食事の無限ループだけでも
くたくたになりますよね。
私の休日はわりと
昼食の、料理、準備、片付け、食器洗い。
それがが済んだと思ったら、今度は、
おやつの準備、片付け、食器洗い。
それが済んだと思ったら、次は、
夕食の料理、準備、片付け、食器洗いと、
調理、準備、片付けループの中に居ることが
多くあります。
なので、子供と遊んでいる時間以外は
台所に立ちっぱなしみたいな日も多いです。
私も妻も(子育てしている方々なら皆さん
同じだと思いますが)けっこうな
ハードワークがずっと
(何年も)続いています。
睡眠不足と心身の疲労で何度も
育児うつっぽくなりました(泣)
子供や妻が深夜の高熱や痙攣
(=熱性けいれん)で
救急車で搬送されたことも、
4、5回ありますし、
そのまま子供が緊急入院となって、
入院先の病院で一晩中、付きっ切りで
徹夜で看病した経験もあります。
(救急隊員さんいつも真夜中の
搬送ありがとうございます)
わが家だけでなく、多くのご家庭でも
そうだと思いますが、
子育てって、ほんとうに大変ですよね。
子供を産み育てるという、私たち人類が、
何百万年もの間、繰り返してきた、
実に普通でありふれたことであるはずの
「子育て」が、なぜ?ここまで大変なのか?
「子育て」が時に、私たちを
育児うつや、育児ノイローゼにさせるくらい、
しんどく苦しいことなのはなぜなのか?
「子育て」が時に、私たちを病院に
救急車で搬送される状況までに
追いこむのは一体なぜなのか?
「子育て」を懸命にしている毎日の中で、
思わずこんな問いが浮かんでしまったことが
ある方も少なくないことと思います。
私も上記のような問いが
何度も心に浮かびました。
「子育て」中の一人の親として、
加えて、カウンセラーとしての
職業的な探求心もあって、
「子育てがなぜ苦しいのか」の
問いの答えを求めて、
私は「子育て」関連の書籍を読み漁り、
動画を観て回り、音声配信を聞いて回り、
専門家を訪ねるなどして、
学びを深めました。
その結果得られた答えは以下のものでした。
それは、現在、多くの私たち、
現代日本人が行っている
「子育て」のスタイルが
「不自然な子育て」だから。
でした。
「不自然な子育て」ではなく、
「自然な子育て」であれば、
子育ての苦しみは、
「不自然な子育て」より
ずっと小さくて済みます。
それでは、
「自然な子育て」と
「不自然な子育て」とは、
どのような「子育て」なのでしょうか。
解説を続けますね。
< 自然な子育て >
私の子育て経験からの実感では、
子供を一人世話するのに、
大人が一人付きっきりになることが
必要だと感じています。
安全が確保された場所であれば、
4歳ぐらいからは、少しは
目が離せることもあると思いますが、
少なくとも、
子供が「おぎゃー」と生まれてから、
満4歳までの4年間は、
片時も子供のそばを離れることも、
目を離すこともできないですよね。
なので、例えば2人の子供を育てるとすると、
子供の世話に2人の大人が必要だと思います。
この片時も子供のそばを離れずに、
子供を見守り続ける、
子育てを担当する大人とは別に、
家事と子育てをサポートする
大人がもう一人必要ですね。
子供に付きっ切りですと
トイレも行けませんからね(泣)
(皆さんもそうだと思いますが)
私も何度も子供と一緒にトイレに入りました。
さらに、仕事をする
(お金を稼ぐ、家計を支える)
大人が一人は必要だと思います。
なので、2人の子供を
「無理をすることなく」
育てるとすると、
子供を見守る大人が2人、
家事を担当する大人が1人、
家計を支えるために働く大人が1人の
合計、4人の大人の力と関りが
最低でも必要だと感じています。
もう一歩踏み込んで理想を言えば、
定期的に自分の時間(!)が取れたり、
子育てに関わる人たちが
体を休める休日を交代で取るためと、
誰かが体調を崩した時に、その人の役割を
代わって引き受けてくれる役割の大人が
もう一人いることが好ましいと思っています。
つまり、子供を2人育てるのには
大人5人の力と関わりが必要だと感じています。
こう実感するくらい、子育ての大変さを
日々、痛感しています(泣)
かつて昭和の中頃までの都市部以外の
日本では、子供2人に大人5人以上の
協力と関りがあったようです。
両親二人と、祖父母の二人、加えて
伯父・叔父や伯母・叔母、いとこ、
子守り役の女の子、
などの存在があったようです。
やっぱり子供の数の2倍以上の大人
(や年長の子供)が力を合わせる、
関わることが子育ての無理の無い自然な姿、
「自然な子育て」だと思います。
「自然な子育て」ができる状態であれば、
育児うつや、育児ノイローゼになることや、
病院への救急搬送を経験することは、
今の「不自然な子育て」の状態より
ずっと少ないだろうと思います。
◆ サルや犬・オオカミもワンオペ育児をしない
ちなみに、人間以外の哺乳類である、
サルとか、犬、オオカミも、
母親がワンオペで子育てすることをしません。
※ワンオペ=ワンオペレーション
一人で(子育てを)担当すること

犬やオオカミは母親以外の
乳母の犬が子犬の世話をします。
群れの他の犬・オオカミたちも
子犬の見守り・教育に参加します。
そうやって出産で力を使い切って
消耗しきっている
母犬(母オオカミ)を休養させます。
サルも、若いメスのサルが、
母親になる練習として順番に子ザル
世話をします。このように、犬、オオカミも
サルもワンオペで子育てはしません。

子供が自立できるようにまでに、
少なくとも10年以上かかるぐらい未熟で、
たくさん(食事、排泄、睡眠などなんにでも)
お世話が必要な状態で生まれてくる人間は、
犬やサル以上に、なおのこと
ワンオペ育児では無く、
子供の数の2倍以上の大人が力を合わせて
子育てすることが必要だと切に感じています。
この、子供の数の2倍以上の大人が
力を合わせて子育てすることが
無理のない「自然な子育て」です。
「自然な子育て」とは、
自然界の育児が必要な生き物たちが
行っている子育てであり、
かつて(100年くらい前まで)の
日本人が実際に行っていた子育ての姿です。
しかし、わが家も含めて、
「子供の数の2倍以上の大人が
力を合わせて子育てする」環境で
子育て出来ている人は多分、
今の日本にはほぼいないんじゃないかな
とも思っています。
今は主流である共働きで子育てされている
ご家庭(子育て世帯の約7割のご家庭)では、
子供の両親である大人2人の役割が
「家計を支える人の役割」として、
一人として計算することが妥当だと思います。
保育園の保育士さんが、
1週間の168時間(=1日24時間×7日間)のうち、
3分の1の50~60時間ぐらい(大人0.3人分)
子供のお世話をしてくれるかと思います。
ただ、保育士さんも、子供一人に付き、保育士さん
一人がいらっしゃることは稀かと思いますので、
保育士さんの「子育て」への関与度は
大人0.2人分ぐらいなのだと思います。
共働きで、主にご夫婦二人だけで
「子育て」されているご家庭では、
家計を支える人(子供の両親2人で)1人
子育てを手伝ってくれる保育士さん0.2人
合計大人1.2人で子育てされている感じが
子育ての実感かと思います。
共働きで子育てされているご家庭では
子供を1人育てるのに、
大人が4人は必要だと感じています。
(子供のお世話をする人が1人
家事と子供のお世話を助ける人が1人)
家計を支える人が2人(共働き))
無理の無い自然な「子育て」をするのに、
4人の大人が必要なところを、
1.2人分の大人で「子育て」をするならば、
人員の充足率は30%しかなく、
人員が70%不足している状況
(「子育て」に関わる大人が
3人も足りない状況)
なので、
子育ての状況としては、
ひどく「不自然な状況」で、
とてもつらい状況であることが
多くあるのだと思います。
共働きの子育てをされているご家庭にせよ、
主婦(主夫)の役割を受け持つ人が居る
子育てをされているご家庭にせよ、
今の日本社会では、あらゆる子育て世帯で、
子育てに関わる人の深刻な人手不足によって、
危機的なぐらい「不自然な子育て」状況が
蔓延していると考えています。
この深刻なほどの「不自然な子育て」状況が、
本来は、親も子どもも、ともによろこびと
温かさをたっぷりと感じることができる
楽しい期間であるはずの「子育て期」を
「不自然なぐらい」非常につらいものに
していると考えています。
子育てが辛すぎる問題、
(引いては少子化問題の一因)の土台には、
この子育てに関わる人の
深刻な人手不足によって、
深刻なぐらい「不自然な子育て」状況が
生まれていることだと考えています。

< カウンセラーが考える子育て >
私は2人の男の子を育てる
一人の子育て中の親として、
子育ての辛さと、またもう一方にある
喜びをビシバシと日々感じています。
また、一人のカウンセラーとしては、
これまでに、10年以上、数百件の
親子問題、子育て問題の解決を
サポートし続けてきました。
その中で、世の中には本当に様々な
家族のカタチ、親子のカタチ、
子育てのカタチがあることを
とても具体的に知ることになりました。
そのカウンセラーとして経験、知見に、
私自身が2人の男の子の父親として
子育てをしている経験が加わって、
・「家族」に笑顔を増やすものは何か?
「家族」から笑顔を減らすもの何か?
・子供が元気に育つ「子育て」って
どうしたらいいの?
これらの問いの答えが
自分の中でかなりハッキリしてきました。
・子供が元気に育つ「子育て」って
どうしたらいいの?
この問に対する私の答えは、
ズバリ!
「親も子供も笑顔になる子育て」
これです。
これが、10年以上、
親子・子育て問題の解決に向き合い続けてきた
カウンセラーである私が考える、子育ての
「目指すべき方向性」であり「ゴール」です。
子供が成長していく過程で、できるだけ
心理的な負担(負債)を背負うことなく、
自己肯定感を育てながら、
(=自分が好き=自分として生きていることが
楽しいと思える心の基盤を育てながら)
自分の人生に元気に集中できるためには、
「子育て」において、子供が笑顔になるだけなく、
親が笑顔になることがセットで必要です。
これまでにカウンセラーとして
何百件と親子問題、子育て問題の解決を、
サポートし続けてきました。
その結果、子供にとってつらく問題になる
親子関係、子育ての仕方について
沢山のケースを知ることとなりました。
また、親側のつらさ、不安、心配に
ついても様々知ることになりました。
この私のカウンセラーとしての経験から
見えてきたことは本当に沢山あります。
どんな子育てが、親や子供から笑顔を失わせ、
子供に心理的な負債を負わせ、
子供の生きる元気を減らしてしまうのか
について見えてきたことがありました。
また、逆に、どんな子育てが
「親も子供も笑顔になる子育て」なのかも
10年以上のカウンセラーの経験から
見えてきました。
その中で、
親や子供から笑顔を失わせる子育てでは無く、
「親も子供も笑顔になる子育て」を
実現するには3つの重要なポイントが
あることに気が付きました。
私は一人の父親として、上記の
「親も子供も笑顔になる子育て」を
実現するために重要な3つのポイントを
日々実践するように努めています。
その結果、「親も子供も笑顔になる子育て」が
おおむね実現できています。
もちろん、だからと言って、
子育てが楽だとは少しも思っていません。
子育ては心身ともに重労働だと実感しています。
(やっぱり、ときおりくたびれ切っています(涙))
私も妻も休みの無い子育ての日々に、
泣きたくなる瞬間がけっこう、沢山あります。
わが家の子供も、
「寝る時間を無視してもっと遊びたい」とか、
「もっと甘いおやつが食べたい」とかの、
子供の意見が通らない時などに、
癇癪を起して泣き喚くことが日々あります。
昼寝から起きた子供の寝起きの機嫌が最悪で、
ぐずる、大泣きする(ギャン泣きし続ける)
のをなだめるのに30分とか1時間とかを費やして、
そのあとの夕食やらお風呂やらの予定が
どんどんぎゅうぎゅう詰めになって
もう泣きそうとかになることもあります。
子供が発熱してぐずって
(発熱の不快感や不安感で不機嫌が極まって)
泣き喚き続けるのを、
エンドレスで何時間も抱っこし続けて、
腕や肩、腰、膝がボロボロになって、
疲れ切って心から感情が無くなることが
数日続くこともありました。
ご飯を食べるというよりは、
子供にご飯を食べさせている隙間で、
何かをつまみ食いするみたいな食事が
毎食続いていくことで、
「食事とは?」と哲学的な疑問が頭をよぎるが、
考えている暇なんてないとかもあります。
子供から、わけの分からない悪口を言われて、
妙に心が傷つくこともあります。
子供がカゼをひいたりして体調が悪い時や、
疲れていて機嫌が悪い時などに、
(具合の悪さゆえの八つ当たりのいじめで)
私に対して言う、
「パパは要らない」
「パパ(の存在が)しんどい」
「(パパじゃ無く)ママに代わって」
「(パパは要らないから)ママが良い」
「(なんでパパが居るの?)ママを呼んできて」
などの、「パパは不要」の拒絶パンチを
まともに食らっては、
「どうせ、自分はただの
(家族にとっての)ATMなんだ」
との思いが浮かんできて、
深く落ち込むこともあります(涙)
などなど、「子育て」中の皆さまの
ご家庭と同じく、毎日がノンストップで
嵐のように過ぎて行っています(泣)
しかし、それと同時に子育ての時間は、
家族と共に心からの笑顔になれる、
充実感に満ちた掛け替えのない
大切な時間だとも感じています。

それではここからは、
「親も子供も笑顔になる子育て」を
実現するために重要な3つのポイント
について解説させて頂きます。
2:「親も子供も笑顔になる子育て」
を実現するために
重要な3つのポイント
まずは「親も子供も笑顔になる子育て」を
実現するために、
重要な「3つのポイント」について
手短で簡潔にお伝えさせて頂きますね。
【1】「親も子供も笑顔になる子育て」を
実現するために、重要な3つのポイントの
<1つ目>は、
「親の個性と子供の個性は、
まるで違う時があることを理解する」
これです。
これは、「親も子供も笑顔になる子育て」を
実現するために知っておくべき基礎であり、
大前提です。
それぐらい重要なことだと思っています。
親の個性と子供の個性は、たとえ親子と
いえども真逆であることさえあります。
そんな時にもし、
「親の個性と子供の個性は
まるで違う時がある」
これを前提とすることができずに、
自分(親)の感覚や基準、価値観を
そのまま子供に当てはめてしまい、
自分の感覚や価値観で子供の行動や状態を
考え、判断してしまうと、
「なんで?そんなことするの!
(私には理解できない!!)」
「どうして?
(私の)言うことを聞けないの!
(私の言うことが正しくて
必要なことなのに、
私の言う通りにしないなんて
おかしい!!)」
こんな思いが湧き出てしまいます。
目の前に居る子供が、自分(親)には
わけが分からない存在となってしまい、
親子関係が混乱してしまいます。
その状態では、子育ては不安と、
イライラだらけで、泣きたくなるようなものに
なってしまうことさえあります。
そんなしんどい状況を回避して、
親も子も笑顔になる子育てを行うためには
「親の個性と子供の個性は、
まるで違う時があることを理解する」
これを子育ての基礎、大前提とする必要があります。
【2】「親も子供も笑顔になる子育て」を
実現するために、重要な3つのポイントの
<2つ目>は、
「親は子供に笑顔を向け続けること
いつでもご機嫌でいること
そのために、自分の機嫌が
良くなることをできる限りすること」
(自分の機嫌が良くなることを
できる限りすることを自分に許すこと)
これです。
これは、「子育て中の親の誰もが
大切にすると良いことのベスト1」
だと思っています。
なぜなら、親から
子供に向けられる親の笑顔は
子供の自己肯定感の成長に直結
しているからです。
自己肯定感が成長することは、
子供の元気の基盤になります。
【3】「親も子供も笑顔になる子育て」を
実現するために、重要な3つのポイントの
<3つ目>は、
「子育てとは保護とトレーニング」
であることを理解する
これです。
子育てについて、
この「保護とトレーニング」の
2つの視点を持つことで、
「子育てって何をしたらいいの?
どこまでしたらいいの?」
この疑問や不安がするりと解けて、
子育てすることが今より
シンプルで気楽になります。
10年以上、親子・子育て問題に
関わり続けてきた心理カウンセラーが考える
「親も子供も笑顔になる子育て」を
実現するために、
重要な3つのポイントをもう一度
ここでまとめると以下の通りです。
【1】
「親の個性と子供の個性は、
まるで違う時があることを理解する」
【2】
「親は子供に笑顔を向け続けること
いつでもご機嫌でいること
そのために、自分の機嫌が
良くなることをできる限りすること」
(自分の機嫌が良くなることを
できる限りすることを自分に許すこと)
【3】
「子育に保護と
トレーニングの視点を持つこと」
「親も子供も笑顔になる子育て」の実現は
この3項目の土台の上にあると思っています。

3:子育てで最重要なのは
親の心からの笑顔?
上記の「親も子供も笑顔になる子育て」の
に重要な3つのポイントをお読み頂き、
すでにお気づきの方も
いらっしゃるとは思いますが、
上記の3つのポイントは
「子供にはこんな言葉をかけて下さいね」
とか
「子供にはこう接してあげて下さい」
のような
子供への直接的な働きかけのノウハウではなく、
子育てで、「親も子供も笑顔になる」ためには
親が子供とどう向き合うことが必要なのか、
親自身の心がけや、
親自身の在り方ついての3項目でした。
特に、親の心身のコンディション(状態)を
良くすることを主な観点とした3項目でした。
日々1日も休むこと無く子育てに向き合う
親の心身のコンディションを良くする、
良好に維持することは、
10年以上親子・子育て問題に
関わり続けてきた心理カウンセラーであり
2児の父親でもある、私が考える
「親も子供も笑顔になる子育て」にとって、
欠かすことのできない土台です。
< 子供は無償の愛を
親に向け続けている >
では、なぜ、私がそう考えているのかと言えば、
「親も子供も心からの笑顔になる」ためには
まずは親が心から笑っていることが必要
だからです。
親の心からの素直な笑顔が
「親も子供も笑顔になる子育て」の
スタート地点です。
親が心から笑えていない時、
子供も心からの笑顔を失います。
なぜなら、子供は常に親の心身の状態を
気に掛けて、親を心配し続けているからです。
カウンセラーとして経験や、
一人の父親としての経験から分かっているのは、
子供は常に無償の愛を親に向け続けています。
このことは、大人になった私達も
また、自分の親の子供であり同じです。
子供にとって、自分が無償の愛を
向け続けている相手である
大好きな親の顔から笑顔が無くなると、
子供は(無意識の内に)どうにかして
親の笑顔を取り戻したいと思います。
親のコンディション(状態)が悪いと
子供はなんとかして親を助けたいと願います。
親の顔に素直な笑顔が戻るまで、
親を心配をし続けるようになります。
子供が、余裕が失われ、笑顔が失われた
親を心配し続けるこの構造は、
子供から親へと向かう愛の流れです。
しかし、それだけではありません。
子供が、余裕が失われ笑顔が失われた
親を心配し続けるこの構造は、
子供から親へと向かう愛の側面だけでなく、
子供の立場にも理由があります。
その子供の立場とは、子供は
親の保護無しでは生き続けることが難しい。
この子供の立場です。
親の元気が失われて、
親が病気で倒れてしまうと、
子供自身も生きていくことが困難になります。
そのため、子供は、生存本能として、
親の心身の状態を常に気遣い、
親の元気を回復させたいと願っています。
これが、子供が親を助けたいと思い続ける、
「子供の立場」からの理由です。
子供は親に無償の愛を送り続け、
自分を守り育ててくれる親を
助けようとし続けます。
これが親子関係における
子供の心の基本構造です。
心理面から観ると、親子関係の基本構造は
以下のようにまとめられます。
親子関係の基本構造
【親】親は子供を守り育てる
(保護育成する)
【子】子供は親に
無償の愛を送り続け、
自分を守り育ててくれる
親を助けようとし続ける
これが心理面から観た親子関係の基礎構造です。
そうは言っても、もちろん、
子供は親を困らせることも沢山します。
親に無償の愛を送り続けている子供が、
親を困らせることをするときの理由を
細かく観て行くなら、
個別に様々な理由がありますが、
大きく分類すると
主に以下の2つのパターンに分類されます。
<1>
子供が発達(成長)の階段を
一歩、一歩、昇っていく
トレーニングに取り組んでいる時
子供が自分の仕事として、
成長の階段を一歩、一歩昇るために、
ひとつ、ひとつ新たな動作を獲得しようと
トレーニングをしている時、
親が想定していない行動や、
子供の経験や認知力の不足から、
危険がある行動を選んでしまい、
親を驚かせたり、困らせたりしてしまう
ことがよくあります。
<2>
子供が無償の愛を向けている親に
裏切られたと感じた時
これは親子関係に
以下のような状態がある時です。
子供の無償の愛に親が応えきれておらず、
親に笑顔が無い、
元気が無い(少ない)状態が
長期化しているため、
「親の笑顔がみたい」という
子供が望む結果が長期間得られていないことで、
子供に不満や悲しみが溜まり、
親に対して「笑顔を見せてもらえない」
不満や悲しみを表現して、
笑顔を見せない親に抗議する
意志を示す方法として、
親を困らせる行動を選択することがあります。
本来は、子供が親を困らせることをするときは、
親に余裕があり、親が元気な時です。
親が元気な時には、
子供は自分の成長に必要なプロセスを
自由に、元気に進みます。
もし、親に余裕も元気も無い時に
子供が親を困らせることが続くのであれば
それは、「子供の強い怒りの表現」である
可能性があります。
その子供の怒り(=「親を困らせる行動」)は、
家族の誰かに、家族の笑顔を減らす
何か間違った行動や考え、判断があり、
それに気づいて変えて欲しいという
子供からの必死なメッセージで
あることが多いです。
この「子供の親に対しての怒り」は
子育てだけなく、家族関係や
子供の成長と将来に渡って重要なテーマですので、
また、別の機会で詳しく解説できればと思います。
親子関係の基本は、
親は子供を守り育てる(保護育成する)。
子供は親に無償の愛を送り続け、
親を助けようとし続ける。
これなので、
親の顔から心からの笑顔が無くなり、
親のコンディション(状態)が悪化すると、
子供は親を心配し、助けようとすることで、
心に大きな負担を抱えることになり、
自分の成長(発達)に集中できなくなります。
心理の観点からの「理想的な子育て」である
「親も子供も笑顔になる子育て」には、
この逆の状態が必要です。
親が心と身体のコンデションを
良好に保つことで、親にはいつも
心からの笑顔がある必要があります。
親の顔に円満な笑顔があることで、
子供は親を心配する
必要が無くなります。
その時、子供が自分の成長や経験に
集中できる環境が整います。
親の顔に円満な笑顔がある環境の中で、
子供は新しい発見や出会いが続く日々を
元気な笑顔で楽しみます。
「親の顔に心からの笑顔があること」が
心理の観点からの「理想の子育て」である
「親も子供も笑顔になる子育て」の基盤です。
それでは、親がどうやって心からの笑顔を
維持し続けたらいいのか?
親の顔を曇らせる子育てへの
不安や疑問を解消して、
迷いなく、子育てに集中できるように
なるためには何が必要なのか?
この質問への答えが、
「親も子供も笑顔になる子育て」
の土台となる前述の3項目です。
以下に再掲させて頂くと、
<1>
「親の個性と子供の個性は、
まるで違う時があることを理解する」
<2>
「親は子供に笑顔を向け続けること
いつでもご機嫌でいること
そのために、自分の機嫌が
良くなることをできる限りすること」
(自分の機嫌が良くなることを
できる限りすることを自分に許すこと)
<3>
「子育に、保護とトレーニングの
視点を持つこと」
これです。
それでは、まずは、
「親子が笑顔になる子育て」
に近づくための3項目の1つ目、
<1>「親の個性と子供の個性は、
まるで違う時があることを理解する」
について解説させて頂きますね。

4:自分の子供が「分からない」と
感じる時にある不安と混乱
どうしたらいいの?
カウンセラーとして、10年以上、
親子・子育て問題の解決をサポート
し続けてきた私の経験からは、
「自分の子供が分からない」
「自分の子供がかわいいと思えない」
と感じられている親御さんは少なくありません。
自分の子供がどうしてこんな行動をするのか
自分には理解が出来ず、不安を感じる
子供の個性や特性にどう向き合っていいのか
分からず、感情的になってしまい、
混乱した出口の無いような気持ちになってしまう
このような子育ての辛さやお悩みを
ご相談頂くことは少なくありません。
< 子供が分からない例 >
- 子供が自分の言うことをきかない
- 自分がして欲しくないことばかりする
- 自分に協力してくれない
- 自分の手間を増やすことばかりする
- いくら言葉で説明しても全く通じない
- 機嫌や態度が突然大きく変わる
- 兄弟・姉妹に対して欲しくないことをする
- 反応や関心が薄い
- 反応が突然で速い
- すぐに飛びつく
- 行動が突発的
- こだわりが強い
- 集中していることを切り替えられない
- 一人で泣き出すまで止められない
- 一人で怒りだすまで止められない
- 気持ちが切り替えられない
- 食べない
- 寝ない
- 着替えない
- 片づけない
- ものを乱暴に扱う
- 靴を履かない
- トイレに行かない
- 歯を磨かない
- 決められたことができたり、
- しなかったりのムラが大きい
- 登園をしぶる、嫌がる
- ずっと話しかけてくる
- 常に見ていて欲しい
- 常に一緒に居て欲しい
- 一緒に居ても笑わない
- 話しかけてこない
- 怖がり、不安が大きい
- 人見知りが強い
- たたく、モノを投げるなどの暴力を使う
など
(< 子供が分からない例 >ここまで)
子供に上記の例のような個性がある時、
親が自分の子供が(なぜそうするのかが)
「分からない」と感じ、
不安な気持ちや、混乱した気持ちに
なってしまうことがあります。
その結果、子供に感情的に接してしまい
大きな声を出す、子供をたたいてしまう
などの、
本当はしたくない行動や態度になってしまい、
自分を責める気持ちで苦しくなってしまった
経験がある方も少なくないと思います。
( 大阪府箕面市の市役所が
行った子育て調査の結果 )
私が住んでいる大阪府箕面市
(人口13万人)の市役所が行った
子育て中の母親・父親、
100人へのアンケート調査結果では、
100人中、約 60人 の母親・父親が
「子供を感情的に叱ってしまう」
「言うことをきかないので
たたいてしまう」
などと回答しています。
本当はしたくないと思っているのに、
子供に感情的に向き合ってしまい
大きな声を出す、子供をたたいてしまう
などをしてしまうのは、
子育て中の多くの親御さんにとって、
共通の悩みです。
心理カウンセリングには、この
「本当はしたくないと思っているのに、
子供に感情的に向き合ってしまい
大きな声を出す、子供をたたいてしまう」
問題の心理的な原因とその解決方法があります。
「親が子供を過剰に怒ってしまう問題」は
子育て分野の心理にとって
とても大きなテーマですので、
また別の機会で詳細に心理面の原因と
解決方法を解説させて頂ければと思います。
今回は、
親が子供を過剰に怒ってしまう問題の
解決にも役立ち、
「親も子供も笑顔になる子育て」の
土台となる考え方である、
「親の個性と子供の個性は、
まるで違う時があることを理解する」
についてまずは解説させて頂きます。
「親の個性と子供の個性は
まるで違う時がある」
これがなんのことかと言うと
上記で例を挙げさせて頂いたような、
親が
「子供が何を考えているのか
まるで分からない」
「子供の行動がどうして
そんなことばかりをし続けるのか
全く理解できずに苦しむ」
この問題の原因である状況のことです。
これは、
「親の個性と子供の個性は
まるで違う」
時に 発生する根深い問題です。
< 例えば・わが家の例 >
わが家の長男は、外見こそは
私より妻に似ているのですが、
中身というか、性格や気質、個性、
行動や言動は、父親である
私に似ているところが多いです。
私と妻の性格や気質、個性は
別な人間同士なので当然なのですが、
いたるところでけっこう大きく違います。
つまり、わが家の長男は、
私と似ているので、
妻とはだいぶ違う個性、気質です。
わが家の長男は、起きている間中、
やんちゃに、動き続け、
ずっと喋り続け、歌い続けています。
1日中ずっと、ママー、パパー、見てー
遊んで―っと、私たちに
呼びかけ続けてくれます(喜泣笑)。
私としては、よく動き、よく遊び、
よく喋る、(というよりはずっと
止まることなく何か喋り続けている)長男は、
休むこと無く動けることができて高性能(?)
だと思いますし、
いかにも子供らしいと思えて
好感を持っています。
とてもかわいいし、見ていて
楽しい気分になれるので、
とても面白いです。
しかし、妻にとっては、
私には子供らしくて
可愛いと思える長男の行動、
やんちゃに動き続けるとか、
ずっと止まることなく
しゃべり続けているなどが、
理解不能で、嫌な気分になって、
イライラしてくるので、
大きな声で叱りたくなるようです。
私には、私の気質と似ている私の長男が、
なんでそこで、妻が思わず怒る行動や、
妻が嫌がる行動を楽しそうにするのかが
それとなく分かって、理解できます。
妻が怒るとか嫌がるとかに関わらず、
長男の行動や言動についれは、
長男がなぜそうするのかが
私にはその気持ちや動機が
「分かるなぁ」と
心の中でよく思っています。
例えば、私には、
長男がおもちゃを乱暴に投げたり、
無理に引っ張たり、壊れるくらいに
無茶に扱ったりする様子や、
周囲の大人には理解できないこだわりで、
一つのことにこだわり続けて、
やがてこだわり過ぎて、
こだわり通りに思い通りにならないことに
一人で泣き出して、
止まらなくなったりすることが、
好奇心や、新しいことへのチャレンジ精神、
やり遂げたいと思う意欲、
成長へのステップと感じられています。
長男が泣いたり、怒ったり(癇癪)する様子に
妻よりびっくりすることも、
イライラすることも少なく、
ゲンナリすることも無く、
「長男は(子供らしくて)かわいいなぁ」
と呑気に思えています。
ところが、私の妻は、そんな長男の
ノンストップに動き続けて、
大人から注意されるようなことを
連発し続けることや、
1日中、際限なく延々に喋り続けていたり、
歌い続けている様子や、
一人で勝手に泣き出すまでのこだわりの強さが
まるで意味が分からないし、
イライラして腹が立って仕方がない。
私の妻も長男のことは大大大好き!
なのですが、
妻は長男の行動や考えていることが理解できず、
躾(しつけ)に手を焼いて、
(何度言っても言うことを聞かずに、
妻が嫌がることや、
理解不能な行動を繰り返すので)
ゲンナリしてしまっていることも多いです。
なので、私の妻はわりと頻繁に
自分の子育ての仕方に自信を無くしたり、
怒りたくはないのに、長男に怒ってばかりの
自分はダメな母親と思って、
自分を責めてしまったりしています。
大大大好きな長男なのに、一緒に居ると
苦しくなってしまうことに混乱したり、
その状況に追い込まれたつらい気分になったり
よくしています。
妻の心境や立場は 本当につらいと思います。
ちなみに、長男は、妻からどんなに怒られても、
「ママ大好きー」と言って
妻ににベタベタしています。
長男にべたべたされている時は、
妻も朗らかな笑顔です。ニコニコです。
日常にそんな場面も多いです。
逆に私は「ママが良い、パパはあっちいけー」
と邪険にされることで、長男が
「ぼく(長男)とママの二人の世界」
を作ることの引き立て役にされています(泣)
私が妻より長男に選ばれる唯一の機会は、
「お風呂」に長男と一緒に入る時です。
長男にとって、妻より私との方が
お風呂で遊ぶ時のテンポが合うようです。
男の子を育てているお母さんには、
私の妻のような経験や悩みを
抱えていらっしゃる方も
少なくないように感じています。
※母親にとっては、
「男の子は宇宙人(と思えるぐらい
よく分からない。理解に苦しむ時が多い)」
と言われることもありますね。
< わが家の例えここまで >
これが、
「親の個性と子供の個性は、まるで違う」
問題です。
つまり、
「子供が何を考えているのか
(自分の感覚、感性、経験からは)
まるで分からない」
「子供が、どうして何度注意しても
自分を怒らせるような行動ばかりを
繰り返し続けるのか
全く理解できずに苦しむ」
この問題です。
私たちの大人で冷静な考えが出来る部分では、
「昔から言われているように、
人は十人十色だから、十人の人がいれば、
十人の別の個性、気質、考えがある。
と実感できていることと思います。
人(もっと言えば動物、植物、
全ての生き物と自然物)の個性は
「千差万別」の言葉がぴったりですよね。
自然の仕組み(生き物の出産含めて)が
作り出したものには
二つとして同じものは無いですよね。
「だから自分と自分の子供の個性が
まるで違って分からないこともあるだろう」
と、頭の片隅や、心のどこかでは
薄々分かっていることもあると思います。
しかし、それでも、どこかの他人ではなく、
毎日、毎日、一緒に近い距離で濃密な時間を過ごす
自分の子供の個性が、自分の個性とまるで違い、
「子供が何を考えているのか
まるで分からないので不安になる」
「子供が、どうして何度注意しても
自分を怒らせるような行動ばかりを
繰り返し続けるのか全く理解できずに苦しむ」
この状態なのはとても辛い毎日ですよね。
この 「親の個性と子供の個性は、まるで違う」
問題は、もう一歩踏み込んで突き詰めると
(1)親と子供の相性の問題
→親子といえども、相性の良し悪しがある
(親子でも個性や気質が合わない時がある)
(2)親の子供への期待値の問題
→「親の子供への期待が大きすぎる問題」です。
「親の子供への期待が
大きすぎる問題」とは、
具体的に言うと、
親が子供に対して、大人と同じように、
言葉で説明されたことを理解して欲しい、
親の意図を汲んだり、親の立場を理解して、
気配りした行動をして欲しいと
(空気を読んで欲しい、察して欲しいと)
「期待してしまう」問題です。
この親が子供に「期待してしまう」状態を
別の角度から言い換えると、
「子供が(大人のように)、
今自分がしたいことをガマンしながら、
周囲に気を配りつつ、
今何をすることが最適なのかを考えながら
振舞うことができると誤解している」
このようにも言える問題です。
私たち大人が日常行っている、
周囲への気配りができることや、
今自分がしたいことをガマンして、
他者が望むことをすることで、
周囲と調和がとれる能力のことを、
「社会性」とか
「社会性の獲得」と言います。
もしくは「モラル(規律)」とも言います。
※<余談>「モラハラ
(モラルハラスメント)」とは
周囲の人が嫌がることをすることで、
「社会性」や「規律(モラル)」が
失われている状態のことです。
「周囲の人が嫌がることをしてはいけない」
これが、現在(2025年)の
私たちの社会(日本社会)が
おおむね共有している価値観なので、
「モラハラ」をはじめ、
様々な「ハラスメント」
(=他者が嫌がることをすること)の
発生が問題視されていますね。
多分、30年前(1980年代頃)の
日本社会では、今より、
「声の大きな人、権力(パワー)が
ある人が強いから
(周囲の人が嫌がることをしても)
わがままが通るよね。
(世の中そんなものだよね)」
の嫌な目に合うことへの
あきらめの傾向が強めで、
「周囲の人が嫌がることをしてはいけない」
(=セクハラ、パワハラ、モラハラなどの
ハラスメント行為や公共の場での
喫煙やポイ捨てなどの迷惑行為は
してはいけない)の価値観は
今より少なめの社会だったように思います。
(余談ここまで)
私たちが「社会性」を獲得するために
必要な脳の認知能力は、
おおむね7才頃から大きく成長し始めると
言われており、その後15才頃までは
未完成であると言われています。
つまり、中学3年生くらいまでは、
「今自分がしたいことをガマンして、
他者が自分に求めること、
期待することをして
周囲と調和がとれることが
他者や自分の得になると」
十分に分からずに、
身勝手な行動をしがちなのが、
人間の自然な成長過程です。
特に7才(小学1年生)までは、
「社会性の獲得」の側面は
まだまだとっても未熟なので、
「今自分がしたいことをガマンして
他の人(親など)が
自分にして欲しいことを優先する」
ことは苦手なのが人間の自然な成長過程です。
※もちろん、個人差は大きくあります。
ですから、親が子供に
「今、子供がしたいことをガマンして
親がして欲しいことを優先して欲しい」
このような期待をすることは、
子供の年齢が小さいほど、
「人間の自然な成長過程の実際」
との差が大きくあり、無理があります。
そもそもは、「社会性の獲得」の
前段階にある、他者にも(自分と同じく)
気持ちや心の痛みがあることが想像できる、
思いやれるようになる認知能力が芽生え始めるのが
おおむね4歳頃からと言われています。
ですから、少なくとも、7才頃までの子供は
脳の発達の都合上(=人類の発達の仕組み上)
大人と較べると思いやりや
配慮に欠ける行動しかとれない
(場合が多い)。
こう言えるかと思います。
(もちろん、7才以下の子供でも、
ときおり(調子の良い時には)
思いやりにあふれる行動や、
自分より他者を優先する行動を
見せてくれますね。)

5:親子といえども相性の良し悪しがある
親と子供には相性の問題が確実にあります。
親と子といえども、相性が良い場合と
相性が悪い場合とがあります。
相性が悪い場合、思わず、
「この子は育てづらい」と感じたり、
「こんなに子供に腹を立てるなんて、
私は母親(父親)失格」などと
悲しくなってしまい易い可能性があります。
上記の私の家の例のように、
私の家では、長男と私は相性が良く、
長男と妻は相性が悪いとも言えます。
(相性の面、「育て易さ」「接し易さ」では、
そうなのですが、長男が好きなのは
私(父親)より圧倒的に私の妻(母親)です。)
長男の父親である私は、
長男と公園で遊ぶのも楽しいです。
長男の母親である妻は、長男と
公園で遊ぶのは何をしていいのか
よく分からないそうで、
長男の遊びを見守っているだけに
なって面白くないそうです。
これは、私の妻だけでなく、
けっこうな割合のお母さんあるあるの
一つでもある、
「子供の公園の見守りつまらな過ぎる問題」
でもあると思います。
ここで上げた例も、父親である私と息子は
「公園遊び」では相性が良い場合が多い、
母親である私の妻と息子は「公園遊び」
では相性が悪い場合が多い。
と言えるかと思います。
自分の子供が
「分からない」と感じる時があり
不安に思ったり、落ち着かない気持ちになって
しまうときには、以下の事実を思いだして
頂くことがおすすめです。
「親の個性と子供の個性は
まるで違うことがあるので、
親子といえども、
相性の悪い場合があったり、
親子といえども、
子供のことが理解できない
ことがあるのが、
普通で、自然で、当たり前なこと」
このことを思い出して頂ければと思います。
例え、子供と相性が悪かったとしても、
子供の行動や考えが理解できなかったとしても、
「子供と相性がぴったりと
合っていることが正解で
子供との相性が悪いことは
正しくない、間違い。」
と思う必要はありません。
「子供の行動や考えが
理解できていることが正解で
子供の行動や考えが
理解できないことは間違いで、
親失格」
とは思う必要もありません。
自分とは異なっていて、よく分からない
子供の個性であったとしても、
攻撃せずに、リラックスした気分で、
愛情をもって見つめてあげて、
子供に笑顔を向けてあげることができれば、
子供はそれで大満足です。
親が子供に向ける心からの笑顔が
子供の自己肯定感の土台を育てます。
「親の個性と子供の個性は
まるで違うことがあるので、
親子といえども、相性の悪いことがあったり、
親子といえども、子供のことが理解できない
ことがあるのが、
普通で、自然で、当たり前なこと」
これを子育ての大前提にして頂くことが、
「親も子供も笑顔になる子育て」の
第一歩だと、10年以上、
何百件の親子・子育て問題の解決を
サポートし続けてきた
カウンセラーとしてはそう言えます。
「親子と言っても別人同士。
全く理解でいないことがある。
それでいい。それは仕方がない。」
「自分には理解できないことをする
子供を許してあげる。
同時に子供が理解できずに
怒ってしまうことがある
自分も責めずに許してあげる。」
この立場に立つことが、
子育てのスタートラインだと思っています。
これはもちろん、
100%完全にそう思える必要はないです。
「自分は子供のことを
100%理解できてなくても良い。
100%は理解できないのだから、
子供の行動や様子が理解出来すに
心配になってもいい。
不安になってもいい。
ときに怒ってしまってもいい。」
こう気持ちを少しでもゆるめて頂いて、
自分を責める気持ちや、
子供を責める気持ちが少しでも
少なくなることがあればうれしく思います。
そうなることで、全ての母親、父親に
少しでも笑顔になれる時間が増えることを
心から願っています。
子供が心から望んでいるのは、
いつでも、いくつになっても、
母親や父親の心からの笑顔なので。
そうは言っても、
「自分の子供の行動や言動が
理解できてなくて、
心配や不安になってしまうことや、
自分でもびっくりするくらい
怒ってしまってまうこと」が
どうしても減らせない、
やめられない。
こんな方もいらっしゃることと思います。
そんな場合には、
お母さんやお父さんが抱えている
「心の傷」に原因がある場合があります。
その「心の傷」を癒すことで、
お子さんの行動や、言動に対する過剰な反応
を減らしたり、無くしたりすることができる
ことがあります。
もし、このことにご関心があれば、
一度、カウンセリングをご利用頂ければと思います。

< 閑話休題の余談2 >
(私の両親、祖父母の子育ての話)
私を育ててくれた、私の両親や祖父母は、
私が4、5才になるくらいまでの
子育てに大変さを感じていたようです。
私の両親や祖父母は、
いくら注意しても言うことを聞かずに
動き回り続けていた私の行動に
ひどく困惑していたみたいです。
その困惑がどれぐらいなことだったのかを示す、
私の体験談を一つご紹介させて頂きます。
◇
私は、自分の子供達がかわいくて
仕方がないです。

親になった私が今、自分の子供達を
すごく可愛いいと感じているように、
私の両親も、幼かった日の私について、
きっと、すごく可愛かった、と
思っていたんだろうなと、
私はある日唐突にそう思いつきました。
そこで、私は意気揚々と
幼い子どもだった頃の私の印象を
両親にたずねて見ました。
もちろん、私は、両親から
「すごくかわいかったよー」
と言ってもらえると
頭のてっぺんから足のつま先まで
そう思っていました。
私は、両親からの
「(お前も子供の頃は)
すごくかわいかったよー」
この一言を聞くために
質問したようなものでした。
早く「(お前も子供の頃は)
すごくかわいかったよー」
を聞かせてーっと思っていた
私への両親からの返事は
私の想定外の返事でした。
両親からの返答は
「おまえ、(おまえを育てるのは)
ほんとにすごく大変だったぞー」でした。
しかも、私が幼い子どもだった頃の印象を、
私が両親にたずねた瞬間に、
両親はこれ以上ないくらいの、
ものすごいしかめっ面になり、
とっても嫌そうな顔までしました。
父も、母も全く同じ反応でした。
えっ、、、なんてことだ(!)
と私は思いました。
それでも私は、
例え私がやんちゃで、ややこしい子で、
育てるのが大変だったとしても
私は、かわいかったはずだと思い、
重ねて両親に、
「でもかわいかったでしょ」と
聞いてみました。
すると、また、私の想定外に、
「いやいやいや、大変だった」と
すごく嫌そうな顔の両親。
「でも、お母さんは気にしなかったよ」
とドヤ顔気味に、自慢げに言う母。
ぼそっと「ありがとう」と私。
うーん、、、。
人生思い通りに
いかないことも多いですね!(笑)
< 余談ここまで >

6:子供への期待値を下げてみる
前述のように、
「親の個性と子供の個性は
まるで違うことがあるので、
親子といえども、相性の悪い場合があったり、
親子といえども、子供のことが理解できない
ことがあるのが、
普通で、自然で、当たり前なこと」
これが親と子の自然な関係性です。
だから、子供を完璧に理解しようと
無理をせずに、子供との相性が悪い
自分を責めたりせずに、
「親の個性と子供の個性は、
まるで違う時があることを理解」して、
「これは仕方がない」と、
「子供を完璧に理解しようとする」ことを
いい意味であきらめて、
「子供を完璧に理解しようとする」こと
以外で親も子もお互いに笑顔になれる
工夫を見つけることに注目することが
必要な時もあると思います。
具体的には、一緒に楽しめることを
見つけることです。
(例)一緒に楽しめることの具体例
・折り紙
・工作(家で子供とできる工作の本が
図書館には沢山あります)
・ボードゲーム
・ニンニクの皮むき、
蒸したジャガイモの皮むきやつぶす工程
白菜をちぎる、クッキーの型抜き、
などの調理のお手伝い
・クイックルワイパーを2本用意して
一緒に掃除
・公園でドングリや
落ち葉を拾って形較べ
・ダンボールを使って基地づくり、
など
(例ここまで)
「親の個性と子供の個性は
まるで違うことがあるので、
親子といえども、相性の悪い場合があったり、
親子といえども、子供のことが理解できない
ことがあるのが、
普通で、自然で、当たり前なこと」
この立場に立つことが、
「親も子供も笑顔になる子育て」の
土台であり、スタート地点だと
思っています。
そうは言っても、
「はい、そうですか。合点承知です!
そう考えて、肩の力を抜いて
気楽に笑顔で子育てしますね」
とは誰もがすぐにはなれないかと思います。
そうなれない背景にある心理的な課題は
人それぞれに多種多様にあると思います。
< 心理的な課題の例 >
(1)
自分は親に個性や考えを尊重してもらえずに、
親の正解を頭ごなしに押し付けられながら
厳しく育てられた。
だから、自分の子供が、
自分が自分の親には許してもらえなかった
親とは違う個性や正解を持つことが
不公平で許せないと感じてしまう。
(自分も(自分の親のように)
子供に自分の考えや正解を
怒りながら押し付けてしまう)
(2)
自分と親の相性がすごく良く、
親子関係が楽しかった。
自分も子供との関係性で
その楽しさが得られるはずと思っていたのに、
実際子育てが始まってみると、
子供との相性が悪く、子供との関係性に
楽しさが少ないことが許せない
(3)
自分の両親や、義理の両親からの
子育てへのプレッシャーがきつくて
子育てに対しての心配が強く余裕が無いので、
子供が自分の理解できないことをすることや、
子供と自分の相性の悪さについて、
おおらかな気分になんてとてもなれない
( 心理的な課題の例ここまで )
などなど、子育てには、
皆さん、人それぞれ、何かしらの
「自分の理想とは程遠い状態」
があるのが現実だと思います。
その中で、前述の、
「親の個性と子供の個性は
まるで違うことがあるので、
親子いえども、
相性が悪いことがある。
親子といえども、子供のことが
理解できないことがある。」
これも、普通で、自然で、
当たり前なこととして
現実に存在しています。
だから、子供を完璧に
理解しようと無理をせずに、
子供との相性が悪い自分を
責めたりせずに、
「親の個性と子供の個性は、
まるで違う時があることを
理解して」
肩の力を抜いて気楽に笑顔で子育てする
それが、
「親も子供も笑顔になる子育て」
のスタート地点です。
しかし、カウンセラーとして多くの
子育て中のお客様をサポ―トさせて
頂いてきた経験からは、
この「親も子供も笑顔になる子育て」
のスタート地点に立つことを
難しく感じられる方々も
少なくないと感じています。
「親の個性と子供の個性は、
まるで違う時があることを
理解して」肩の力を抜いて
気楽に笑顔で子育てする
実は、これが難しいと感じられる
多くの方々に共通する
「心理面の理由」があります。
それは、
「子供への期待値が
上がり過ぎてしまう」
問題です。
言い換えると、
「子供が子供であることを
忘れてしまう」
問題ですし、
無意識、無自覚のうちに、
「子供を大人と同じように
考えてしまう」
問題です。
< 子供を大人扱いしない >
4歳以下の子供は、生まれてから
まだわずか数年の存在です。
大人と較べるとすべての知識、
経験値が圧倒的に少ないです。
脳の認知機能も10才~12才頃までは未完成で、
自分の目の前に広がる世界についての理解度や
認識度合について大人とは大きく差があります。
※「 認知機能 とは、
・知覚(五感で知る感覚のこと)、
・想像力、推論(AだからBだろうと推測)する力、
・判断力 ・決定力 ・記憶力
・言語理解力
(=実際には目の前には存在していないが
言語で表現されたこと(=概念)を理解する力)
などの脳などの働きを指す総称」
そんな人間として成長途上の、
未完成な状態である子供が生活する環境は、
家の中も、家の外も、基本的には、
全てが大人向けに作られています。
子供向けの特別な作りではない限り、
子供には何事も簡単にはできないように
出来ています。
その子供の日常生活の困難さを想像するには、
全てが現状の2倍のサイズになっている、
家や屋外で生活する様子をイメージすると
分かり易いかと思います。
階段、トイレ、ソファー、リモコン、
テーブルの高さ、蛇口までの距離、
歩道の段差、車や自転車の大きさなどなど
何をするにつけ、今の2倍のサイズ、
2倍の距離感があるのは、
まずもって大きさに圧倒されますし、
とても不便ですし、使いこなすことに
難しさを感じますよね。
それが子供の日常の生活感覚です。
< 子供の日常生活の例1 >
(以下のものが大人用で、子供用ではない)
・家や外の施設の扉の大きさや重さ
・トイレの大きさ(子供用サイズの
トイレもあるところにはある)
・テーブルやイスのサイズ
(飲食店ではお子様イスがありますね)
・交通ルールや、道路の設計
< 子供の日常生活の例2 >
例えばお片付け。
子供の認知機能では、
目の前に散乱しているおもちゃが
積み木なのか、ブロックなのか、
おままごとセットなのかが
大人ほど、くっきり明確に
分類できていないと考えられます。
そのうえ、積み木、ブロック、
おままごとセットを
それぞれ片づける場所や
入れ物(容器、箱)の差異も、
(大人側で子供でも
すぐに分かる工夫をしていなければ)
明確に分かっていないことも考えられます。
そのために、子供はおもちゃの
お片付けについて、
大人が考える何倍もの複雑さや
難易度を感じていると考えられます。
なので、「おもちゃのお片付け」を
「自分の手には負えない」
「意味が分からない」と
感じてあきらめてしまう
(逃げ出したり、無視する、)
子供も多いかと思います。
( 例ここまで )
この大人である私たちと子供の認知機能や
身体的機能(手先の器用さや力加減の感覚などの)
差異を理解して、子育ての前提とすることが、
「子供を大人扱いして」
「子供への期待値が
上がり過ぎてしまう」
ことを予防してくれます。
しかし、大人である私たちと子供の認知機能や
身体的機能(手先の器用さや力加減の感覚などの)
差異を理解したとしても、
「子供への期待値が上がり過ぎてしまう」
ことを自分では止めることができずに、
子供に過度な期待を抱いてしまい、
自分の期待通りにしない、出来ない
子供に対してイライラし続けて
しまうことがあります。
この「子供は大人と同じにはできない。
それどころか、子供はまだ脳などの
認知機能にせよ、身体機能にせよ、
あらゆることが発達の途上なので、
大人が思っているより、全てのことに
複雑さと難しさを感じている」ことが
分かっているのに、
自分がして欲しいことができない、
しないことが自然な状態である子供に
(子供ができること、
子供にして欲しいことの
期待値が上がってしまい、)
イライラしてしまうことがどうしても
止まらない背景には、
親の心の中に
未解決な課題が存在している
ことが原因となっている場合が多いです。
< 親の心の中にある未解決な
心理面の課題の例 >
■ 【 心の傷(トラウマ)】
■ 親に自分の個性や考えを尊重してもらえずに、
親の正解を押し付けられることをガマンして
耐えてきた
■ 親が自分の期待を押し付けてくる人だった。
その期待に応えようと頑張り続けて苦しんだ
■ 親や周囲から「いい子」で居ることが
求められていたり、
「いい子」でいることが親や周囲からの
評価が高かったので、
「いい子」の役割を意識しながら過ごす日々に
窮屈さや自分の無さを感じていた
■ 【 家族連鎖 】
■ 子供にはイライラしながら向き合う習慣が、
親、祖父母など、代々続いている
■ 子供に「ちゃんとしている」ことや、
「いい子」であることを求めることが
親や、祖父母など代々続いている
■ 【 罪悪感 】
■ 心の中に「罪悪感」を抱えているため、
目の前の幸せを受け取ることが
難しくなっている
そのため、子供という大切な存在が居る
幸せを受け取りづらくなっている
その結果、「子供」という
仲良くしたい存在と
不仲になるための(無自覚の)工夫として、
「子供への期待値を上げ過ぎる」ことで、
いつも子供にイライラすることを続けてしまう
(「親の心の中にある未解決な
心理面の課題の例」ここまで)
上記でご紹介させて頂いたような
「子供への期待値が上がり過ぎてしまう
親側の心理面の課題」があると、
子供への期待値をうまく下げることが
できません。
「子供への期待値」が下がらないので、
あれもできて欲しい。
こうあるべきだ。
親に協力するのが当然。
となり易いです。
上記のような「子供に対しての
親の大きすぎる期待」は
当然に叶うことが無く、がっかりして、
イライラしてしまうことが多いです。
カウンセリングでは「子供への期待値」が
下がらない心理面の課題を見つけ出して
解消することをサポートすることができます。
心理面の課題を解決することで、
「子供への過剰な期待」が手放なされ、
「子供への期待値」を下げることができます。
「子供への期待値」が下がることで、
手に入る変化は、下記です。
<「子供への期待値」が
下がることで手に入る変化 >
- 子供を怒らずにすむ
- 子供と言い争わなくなる
- 子供に心配されずにすむ
- 子供のストレスを減らすことができる
- 子供をほめることがしやすくなる
- ほめることで子供の成長が促進される
- 子供の自己肯定感の成長が順調になる
- 子供と一緒に笑顔で居られる時間が増える

<今回のまとめ・ふりかえり>
これまでに10年以上、
親子・子育て問題の解決を
サポートし続けてきたカウンセラーが考える、
「親も子供も笑顔になる子育て」
を実現するために、
重要な3つのポイントの<1つ目>は、
「親の個性と子供の個性は
まるで違う時があることを理解する」
これでした。
これは、
「子供のことが理解できない自分も
自分には理解できない子供も、
一緒に許してあげる」
この意味でもあります。
自分と子供とは個性や感性が全く違う
別人であることを前提にして、
子供のことが分からないと感じる
自分を責めたりせず、同時に、
自分には分からないことをし続ける
子供を責めたり、イライラしないことが
大切だと思っています。
みなさんもすでにご存じのように
自分や子供を責めたり、イライラしても、
子供や自分がその分より多く
成長するわけではありませんね。
「親の個性と子供の個性は
まるで違う時がある」
このことを頭では十分に理解していても、
自分とは違う個性や考え、感覚を持つ子供、
自分の思い通りに動いてくれない子供に
イライラすることが止まらない時や、
どうしても子供にイライラしてしまう、
自分を責めてつらくなってしまう時には、
その原因として、深層心理に心の課題を
抱えてしまっていることがあります。
分かっていてもやめられない習慣がある。
衝動的になってしまい、どうしても
自分止めることができない時がある。
自分を変えたいのに変えられない。
こんな困り事が生まれてしまう原因は、
自分の深層心理に残っている、
古いガマンや、過去のストレスや、
心の古傷(トラウマ)などが原因と
なっていることがあります。
カウンセリングを利用すると、
深層心理に残っている
古いガマンや過去のストレスを解消したり、
心の古傷を癒やしたりすることができます。
そのことで、子育てのイライラや、
自分を責めてしまう苦しさを
一つ、一つ減らすことができます。
子育てのイライラや、
自分を責めてしまう苦しさにお困りの方は
カウンセリングのご利用をご検討いただき、
「親も子供も笑顔になる子育て」に
一歩、一歩近づいて行くことの
お力にならせて頂ければありがたく思います。
< 次回の予告 >
それでは、これまでに
10年以上、親子・子育て問題の解決を
サポートし続けてきたカウンセラーが考える、
「親も子供も笑顔になる子育て」を
実現するために、重要な3つのポイントの
<2つ目>、
「親は子供に笑顔を向け続けること
いつでもご機嫌でいること
そのために、自分の機嫌が
良くなることをできる限りすること」
(自分の機嫌が良くなることを
できる限りすることを自分に許すこと)
「親も子供も笑顔になる子育て」を
実現するために、重要な3つのポイントの
<3つ目>、
「子育てとは保護とトレーニング」
であることを理解する
はまた次回の記事でお伝えさせて頂きますね。
次回の記事もどうぞよろしくおねがいします。
最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
※次回の記事は準備中です